この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
11 双胎妊娠について正しいのはどれか。
1.二絨毛膜双胎は二卵性双胎と診断する。
2.胎囊が2つあれば二絨毛膜双胎と診断する。
3.単胎妊娠に比べて胎児形態異常の発生頻度は低い。
4.膜性診断ができない場合は二絨毛膜双胎として管理する。
解答2
解説
多胎妊娠とは、2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠することをいう。 双胎妊娠とは双子のことを指す。双胎妊娠には①一卵性双胎と②二卵性双胎とがある。②二卵性双胎は2個の受精卵から発生したもので、2個の胎盤があり、二絨毛膜二羊膜となる。一卵性双胎は1個の受精卵が分裂することにより発生し、分裂の時期により二絨毛膜二羊膜、一絨毛膜二羊膜、一絨毛膜一羊膜のいずれかになる。
1.× 逆である。「二卵性双胎」は、「二絨毛膜双胎」と診断する。なぜなら、二絨毛膜双胎と診断されても、二卵性双胎である可能性が高いが、早期に分裂した一卵性双胎である可能性も否定できないため。
・双胎妊娠には①一卵性双胎と②二卵性双胎とがある。②二卵性双胎とは、2個の受精卵から発生したもので、2個の胎盤があり、二絨毛膜二羊膜となる。一方、①一卵性双胎は、1個の受精卵が分裂することにより発生し、本症例の1絨毛膜2羊膜(胎児の間に隔壁があり)、1絨毛膜1羊膜(胎児の間に隔壁がなし)のいずれかになる。
2.〇 正しい。胎囊が2つあれば二絨毛膜双胎と診断する。なぜなら、胎囊は絨毛膜によって形成されるため。したがって、胎囊が2つ存在するということは、それぞれが独立した絨毛膜を持っていることを意味し、二絨毛膜双胎の最も早期かつ確実な超音波診断基準となる。
・胎囊とは、受精卵が子宮に着床した後に形成される、胎児と羊水を含む袋状の構造である。
3.× 単胎妊娠に比べて胎児形態異常の発生頻度は「低い」ではなく高い。なぜなら、受精卵の分裂過程における異常や、胎盤・臍帯の異常、胎児同士の血流の不均衡(双胎間輸血症候群など)が影響するため。双胎妊娠では悪阻(つわり)、早産、妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群、HELLP症候群、子宮内胎児発育遅延、胎児形態異常、子宮内胎児死亡、血栓症などの合併症が単胎妊娠に比べて起こりやすい。特に、早産は多胎妊娠では頻度が高く、双胎妊娠の児の予後に大きく関わる合併症である。
4.× 膜性診断ができない場合は、「二絨毛膜双胎」ではなく一絨毛膜双胎として管理する。なぜなら、一絨毛膜双胎は、双胎間輸血症候群(TTTS)や選択的胎児発育不全(sIUGR)、一絨毛膜一羊膜双胎の臍帯の絡まりなど、特有の合併症リスクが高く、より厳重な管理(頻繁な超音波検査など)が必要であるため。
・多胎妊娠の膜性診断とは、妊娠中に胎児の膜の数を数えて、胎児どうしの関係を特定する診断である。胎児の膜には絨毛膜と羊膜があり、胎児の膜の構成によって、一絨毛膜二羊膜双胎、二絨毛膜二羊膜双胎、一絨毛膜一羊膜双胎などの種類に分類される。
12 Aさん(32歳、初産婦)は陣痛開始から12時間が経過した。このときの内診所見は、子宮口7cm開大、展退度80%、Station±0、小泉門は触れず、大泉門が先進部として触れた。
この場合に予測される骨盤通過面はどれか。
1.小斜径周囲面
2.前後径周囲面
3.大斜径周囲面
4.気管頭頂径周囲面
解答2
解説
・Aさん(32歳、初産婦、陣痛開始から12時間)
・内診所見:子宮口7cm開大、展退度80%、Station±0、小泉門は触れず、大泉門が先進部として触れた。
→本症例は、 分娩第1期の活動期後半で胎児は前頭位(小泉門は触れず、大泉門が先進部)である。ちなみに、Station±0は、坐骨棘の高さ、つまり胎児先進部が中骨盤にある状態である。
1.× 小斜径周囲面での通過は予測されない。なぜなら、Aさんの内診所見では大泉門が先進部であるため。通常は、児の頭部が最も縮まるべき径である。
・小斜径とは、後頭部の一番下(後頭結節)から、大泉門(前頭部の最前部)までの距離である。
2.〇 正しい。前後径周囲面は、この場合に予測される骨盤通過面である。なぜなら、本児のように前頭位の場合、児の頭部の前後径(後頭部と鼻根を結ぶ径)が最も大きく、これが骨盤内を通過しようとするため。この径は通常、骨盤のどの径よりも長いため、難産になりやすい。
・前後径とは、胎児の頭の前後の長さ(前後方向の直径:後頭部と鼻根を結ぶ径)を指す。よく前後径は、胎児の頭が産道をスムーズに通過できるかを判断する基準として使われる。
3.× 大斜径周囲面での通過は予測されない。なぜなら、Aさんの内診所見では大泉門が先進部であるため。
・大斜径とは、オトガイから小泉門より3cm前方の点を結んだ径線である。
4.× 気管頭頂径周囲面での通過は予測されない。なぜなら、Aさんの内診所見では大泉門が先進部であるため。
・気管頭頂径とは、その名の通り、気管から頭頂までの距離である(あまり使用されない)。
13 養親となることを希望している者への特別養子縁組制度の説明で正しいのはどれか。
1.「養親は育児休業を取得できません」
2.「実親が育てたいと言った場合は、実親の元に戻ります」
3.「原則、養子になった子どもとの親子関係は解消できません」
4.「将来子どもが戸籍を見ると、養子であることが分かります」
解答3
解説
特別養子縁組とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度である。特別養子縁組は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立する。(※参考:「特別養子縁組制度について」厚生労働省HPより)
1.× 養親「も」育児休業を取得することができる。なぜなら、養子縁組によって形成された親子関係を法的に保護し、養親が安心して育児に専念できる環境を保障するため。
・育児休業とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことであり、男性も取得可能である。育児休業は『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)』に規定されている。育児休業は、子の父母のいずれもが対象となり、父母本人の申し出により適用される。
2.× 実親が育てたいと言った場合でも、原則、「実親の元に戻ることはない」。なぜなら、特別養子縁組は、実親子関係を終了させ、養親子関係を新たに確立することを目的としているため。
3.〇 正しい。「原則、養子になった子どもとの親子関係は解消できません」と伝える。なぜなら、選択肢2と同様、特別養子縁組は実親子関係を終了させ、養親子関係を形成する制度であるため。特別養子縁組は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立する。(※参考:「特別養子縁組制度について」厚生労働省HPより)
4.× 将来子どもが戸籍を「見ても」、養子であることが「分からない」。なぜなら、特別養子縁組における戸籍の記載は、実子と同様に扱われるため、養親の戸籍に「長男」「長女」などと記載されるため。
14 母体の致死率が高く、妊娠を避けるべき循環器系の病態はどれか。
1.肺高血圧症
2.肺血栓塞栓症の既往
3.心室中隔欠損症の修復後
4.NYHA心機能分類Ⅰ度の心不全
解答1
解説
1.〇 正しい。肺高血圧症は、母体の致死率が高く、妊娠を避けるべき循環器系の病態である。なぜなら、妊娠中は、循環血液量の増加、心拍出量の増加、子宮収縮などにより、心臓への負担がさらに増大するため。したがって、肺高血圧症の妊婦は心不全、致死的な不整脈、血栓症などの合併症を発症しやすく、母体死亡率が25〜50%と極めて高い。原則として妊娠は禁忌とされている。
・肺高血圧症とは、肺動脈の血圧が異常に高くなる病気で、肺の血管が狭くなったり硬くなったりすることで、心臓(特に右心)に大きな負担がかかるものである。
2.× 肺血栓塞栓症の既往は、妊娠が禁忌とはいえない。なぜなら、リスクはあるものの適切ない医療ケアで妊娠が継続できるケースがほとんどであるため。
・肺血栓塞栓症とは、肺の血管(肺動脈)に血のかたまり(血栓)が詰まって、突然、呼吸困難や胸痛、ときには心停止をきたす危険な病気である。ロング・フライト血栓症やエコノミークラス症候群などと呼ばれる。離床(車椅子乗車や立位訓練、歩行訓練など)を開始したタイミングで発症するリスクが高くなるため注意が必要である。多く原因は、足の深いところにある静脈(深部静脈)に血液の塊である血栓ができて、その血栓が血流に乗って心臓を介して肺動脈に詰まることである。
3.× 心室中隔欠損症の修復後は、妊娠が禁忌とはいえない。なぜなら、心室中隔欠損症の修復後であれば、心臓への負担は軽減され、多くの場合、通常の妊娠・分娩が可能であるため。
・心室中隔欠損症とは、心室を隔てる壁に穴が開いているため血液の交通が生じる病気である。欠損を通る血液は左心室から右心室へ流れ、肺動脈に血液が多く流れることにより、肺うっ血や肺高血圧を引き起こす。
4.× NYHA心機能分類Ⅰ度の心不全は、妊娠が禁忌とはいえない。なぜなら、リスクはあるものの適切ない医療ケアで妊娠が継続できるケースがほとんどであるため。Ⅲ度~Ⅳ度にて、妊娠は禁忌となる(「心疾患患者の妊娠・出産の適応,管理に関するガイドライン」日本循環器学会様HPより)。
Ⅰ度:心疾患があるが、身体活動には特に制約がなく日常労作により、特に不当な呼吸困難、狭心痛、疲労、動悸などの愁訴が生じないもの。
Ⅱ度:心疾患があり、身体活動が軽度に制約されるもの。安静時または軽労作時には障害がないが、日常労作のうち、比較的強い労作(例えば、階段上昇、坂道歩行など)によって、上記の愁訴が発言するもの。
Ⅲ度:心疾患があり、身体活動が著しく制約されるもの。安静時には愁訴はないが、比較的軽い日常労作でも、上記の主訴が出現するもの。
Ⅳ度:心疾患があり、いかなる程度の身体労作の際にも上記愁訴が出現し、また、心不全症状、または、狭心症症候群が安静時においてもみられ、労作によりそれらが増強するもの。
15 妊娠糖尿病の妊娠管理で正しいのはどれか。
1.食事療法として2分食を指導する。
2.薬物療法としてインスリン療法を行う。
3.薬物療法として経口血糖降下薬を内服する。
4.食前血糖120mg/dL以下を目指して指導する。
解答2
解説
妊娠糖尿病とは、妊娠中にはじめて発見、または発症した糖尿病まではいかない糖代謝異常のことである。糖代謝異常とは、血液に含まれる糖の量を示す血糖値が上がった状態である。肥満女性は妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、帝王切開分娩、巨大児などのリスクが高い。
1.× 食事療法として、「2分食」ではなく3分食を指導する。なぜなら、妊娠糖尿病では、血糖値の急激な上昇を抑えるため。1日3食に加えて、間食(補食)を2〜3回加える5〜6分食が推奨される。2分食(朝食と夕食のみ、あるいは昼食と夕食のみなど)では、食事と食事の間隔が長くなりすぎて低血糖のリスクが高まるか、一度に摂取する量が多くなりすぎて食後高血糖を招きやすくなる。
2.〇 正しい。薬物療法としてインスリン療法を行う。なぜなら、インスリンは胎盤を通過せず、胎児への影響が少ないため。食事療法と運動療法で血糖コントロールが不十分な場合、薬物療法が必要となる。
3.× 薬物療法として、「経口血糖降下薬」ではなくインスリン薬を内服する。なぜなら、経口血糖降下薬は胎盤を通過し、胎児への影響(胎児に低血糖や催奇形性などの悪影響)が懸念されるため
4.× 「食前」ではなく食後2時間血糖120mg/dL以下を目指して指導する。日本糖尿病学会においては、妊娠中は、朝食前血糖値70~100mg/dL以下、食後2時間血糖値120mg/dL以下、HbA1c:6.2%未満を目標とする。一方、日本産婦人科学会によると、目標血糖値は「早朝空腹時血糖値95㎎/dL未満かつ食後1時間血糖値140㎎/dL未満,もしくは食後2時間血糖値120㎎/dL未満」となっている。
妊娠すると、胎盤から分泌されるホルモン(ヒト胎盤性ラクトゲン(HPL)、 プロゲステロン、 エストロゲン)の影響でインスリン抵抗性が強くなる。インスリン抵抗性とは、インスリンは十分な量が作られているけれども、効果を発揮できない状態である。運動不足や食べ過ぎが原因で肥満になると、インスリンが働きにくくなることを指す。「インスリンの抵抗性が強くなる」ということは、つまり糖を効率よく取り込めない(分解できない)ことを意味する。したがって、連鎖的に下記の①~③のことが起こる。
①インスリンの過剰分泌→②食後血糖の上昇→③空腹時血糖の低下
糖質異常を有する妊婦の血糖コントロールは、低血糖のリスクを最小限にとどめ、可能な限り健常妊婦の血糖日内変動に近づけることを目標とする。これまでの報告では、食事療法やインスリン療法、血糖自己測定などを行い、良好な血糖値を維持することで、母児の予後が良好になることが示されている。血糖を厳格に管理するためには、血糖自己測定を活用し、適切な食事療法、運動療法、薬物療法(インスリン)を行っていくことが重要である。
 希望の解説ブログ
希望の解説ブログ 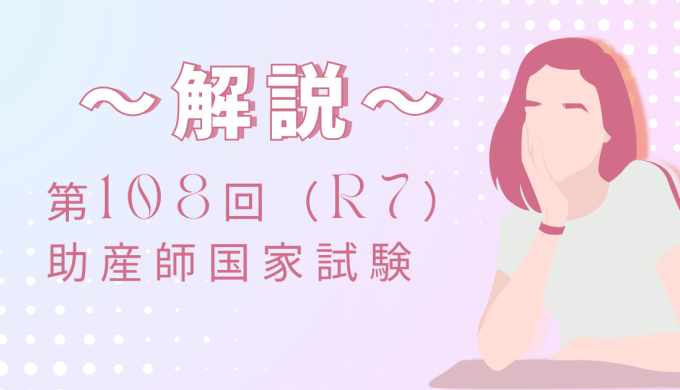


日本産婦人科学会によると、目標血糖値は「早朝空腹時血糖値95㎎/dL未満かつ食後1時間血糖値140㎎/dL未満,もしくは食後2時間血糖値120㎎/dL未満」となっています。以前は解説に記載してある数値だったそうですが、現在は改訂されています。
コメント・ご指摘ありがとうございます。
確かに、以前は「食後2時間120mg/dL以下」だけが強調されていましたが、現在の日本産婦人科学会の指針では「空腹時95mg/dL未満」や「食後1時間140mg/dL未満」も明記されていますね。
一方で、日本糖尿病学会の方では、朝食前70〜100mg/dLと少し幅を持たせた表現になっている点や、HbA1c 6.2%未満の基準も特徴的です。
つまり、「どの学会の基準を採用するか」で微妙に数値が異なるため、試験対策では「どの学会基準か」を意識して覚えることが重要になりそうですね。
それらも踏まえ、修正させていただきましたので、またご確認ください。
今後ともよろしくお願いいたします。