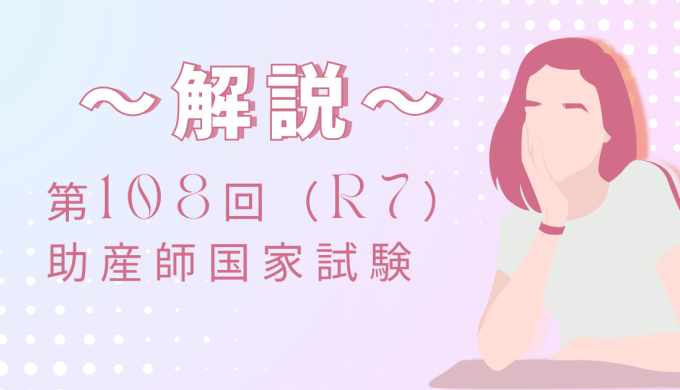この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
1 産後の授乳について母乳栄養または人工栄養にするか迷っている初妊婦に対して、助産師は具体的な授乳のイメージができるように説明し「一緒に考えましょう」と伝えた。
このときの助産師の対応は、倫理原則のうちどれか。
1.正義
2.善行
3.無危害
4.自律尊重
解答4
解説
医療倫理の四原則は、トム・L・ビーチャムとジェイムズ・F・チルドレスが『生命医学倫理の諸原則』で提唱したもので、医療従事者が倫理的な問題に直面した時に、どのように解決すべきかを判断する指針となっています。
・自律性の尊重(respect for autonomy)
・無危害(non-maleficence)
・善行(beneficence)
・公正(justice)
(引用:「医療倫理」厚生労働省HPより)
1.× 正義の原則とは、公平な資源の配分を行うことであるため。正義の原則とは、全ての患者に対し、患者ニーズに応じて、適正かつ公平なヘルスケア資源の配分を行うことである。
2.× 善行の原則とは、患者のために善をなすこと、最善を尽くすことである。ここでは、医療従事者側が考える善行ではなく、患者が考える最善の善行を行うというものである。例えば、患者の症状に合った治療方法があれば、できうる最良の治療をすることをいう。
3.× 無危害の原則とは、患者に危害を及ぼさないことである。また、今ある危害や危険を取り除き、予防することも含まれる。例えば、①体に侵襲が少ない(傷つけない・影響が少ない)治療方法を可能な限り選択する。②糖尿病によって足の指が壊疽したが、足全体に壊疽が広がらないよう切断することがあげられる。
4.〇 正しい。自律尊重が該当する。なぜなら、助産師が「具体的な授乳のイメージができるように説明」することで情報を提供し、「「一緒に考えましょう」と伝えた」ことで母親が主体的に意思決定するプロセスを支援しているため。
・自律尊重の原則とは、患者が自己決定できるよう必要な情報を提供するとともに、患者が決定した内容を尊重し、それに従うことである。
2 妊婦の摂取量が過量な場合に、有機水銀による胎児の健康障害が最も懸念される魚介はどれか。
1.サバ
2.ブリ
3.カツオ
4.クロマグロ
解答4
解説
有機水銀は特に胎児の中枢神経の発達に影響を及ぼすとされている。妊婦、幼児、近く妊娠を予定されている方は、有機水銀濃度が高い水産物を主菜とする料理を週1回以内(合計で週におおむね50~100g程度以下)にすることをお勧めしている。主に多くの有機水銀が含まれるものとして、マグロ類(マグロ、カジキ)、サメ類、深海魚類(キンメダイ、ムツ、ウスメバルなど)、鯨類(鯨、イルカ)などがあげられる。ちなみに、サンマ、イワシ、サバなどは、一般的に有機水銀濃度が低い水産物であるため、控える必要はない。
①四日市喘息(三重県):主に亜硫酸ガスによる大気汚染を原因。
②新潟水俣病:有機水銀(メチル水銀)による水質汚染や底質汚染を原因。
③イタイイタイ病(富山県):カドミウムによる水質汚染を原因
④熊本水俣病:有機水銀(メチル水銀)による水質汚染や底質汚染を原因
1.× サバは、比較的リスクの低い魚介類に分類される。なぜなら、有機水銀は、寿命の長い魚ほど蓄積しやすい傾向があるため。サバは比較的小型で寿命も短いため、体内に蓄積されるメチル水銀の量が少ない傾向にある。
2~3.× ブリ/カツオは、有機水銀の含有量が中程度である。選択肢4.クロマグロほど高い懸念はないが、摂取量には注意が必要である。
4.〇 正しい。クロマグロが、妊婦の摂取量が過量な場合に、有機水銀による胎児の健康障害が最も懸念される魚介である。なぜなら、クロマグロは非常に大型で寿命が長く、他の魚を大量に捕食するため。したがって、体内に高濃度のメチル水銀が蓄積されやすい特性がある。

(※図引用:「これからママになるあなたへ」厚生労働省HPより)
3 Aさん(54歳、女性、専業主婦)は夫と2人暮らしである。趣味は読書で家事以外で家から出ることは少ない。
Aさんが運動不足によってリスクが高くなる健康問題はどれか。
1.1型糖尿病
2.子宮内膜症
3.腹圧性尿失禁
4.メタボリックシンドローム
解答4
解説
・Aさん(54歳、女性、専業主婦)
・夫と2人暮らし。
・趣味:読書、家事以外で家から出ることは少ない。
→ほかの選択肢が消去できる理由もしよう。
1.× 1型糖尿病よりリスクが高いものがほかにある。なぜなら、1型糖尿病は、遺伝的要因やウイルス感染などが関与するため。生活習慣(運動不足や食生活)が原因となるのは、2型糖尿病である。
・1型糖尿病とは、原因が自己免疫異常によるインスリン分泌細胞の破壊などがあげられる糖尿病である。小児~思春期の発症が多く、肥満とは関係ないのが特徴である。一方、2型糖尿病の原因は生活習慣の乱れなどによるインスリンの分泌低下である。
2.× 子宮内膜症よりリスクが高いものがほかにある。なぜなら、子宮内膜症は、ホルモン(特にエストロゲン)の影響や免疫系の異常、遺伝などが複雑に絡み合って発症すると考えられているため。
・子宮内膜症とは、子宮の内側の壁を覆っている子宮内膜が、子宮の内側以外の部位に発生する病気である。腰痛や下腹痛、性交痛、排便痛などが出現する。経口避妊薬を内服することによりエストロゲンの総量が低く抑えられ、排卵を抑制し、子宮内膜症の症状を軽減し、子宮内膜症予防にもなる。なお、乳癌や子宮内膜癌などのエストロゲン依存性悪性腫瘍や子宮頸癌及びその疑いのある場合は腫瘍の悪化あるいは顕性化を促すことがあるため禁忌となっている。
3.× 腹圧性尿失禁よりリスクが高いものがほかにある。なぜなら、腹圧性尿失禁は、出産経験、加齢、肥満などが主なリスク因子となるため。
・腹圧性尿失禁とは、腹圧をかけるような運動時(重い荷物を持ち上げたときなど)に尿が漏れる状態で、男性よりも女性に多くみられる。尿道括約筋を含む骨盤底の筋肉が弱くなることが原因で、加齢、出産、喫煙、肥満などと関連している。
4.〇 正しい。メタボリックシンドロームは、Aさんが運動不足によってリスクが高くなる健康問題である。なぜなら、運動不足は、エネルギー消費を減少させ、内臓脂肪の蓄積を促進し、インスリン抵抗性を高めるため。
・メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積を基盤とし、動脈硬化の危険因子を複数合併した状態のことである。
①腹部肥満(ウエストサイズ 男性85cm以上 女性90cm以上)
②中性脂肪値(HDLコレステロール値 中性脂肪値 150mg/dl以上、HDLコレステロール値 40mg/dl未満のいずれか、または両方)
③血圧(収縮期血圧130mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上のいずれか、または両方)
④血糖値(空腹時血糖値110mg/dl以上)
4 卵胞の発育で正しいのはどれか。
1.排卵時の卵胞の直径は3~5mmである。
2.初経のころの原始卵胞数は出生時より少ない。
3.排卵されなかった卵胞はグラーフ卵胞となる。
4.プロゲステロンの作用によって排卵に至る卵胞が1つになる。
解答2
解説
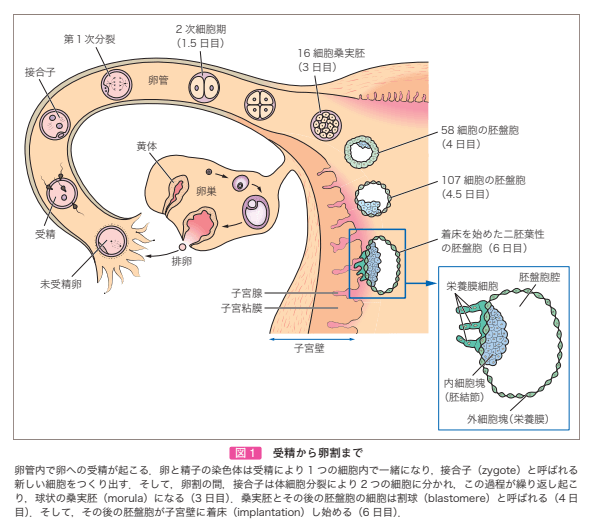
(※図引用:「基礎編―人体発生―」腹腔内内ヘルニア大全HPより)
1.× 排卵時の卵胞の直径は、「3~5mm」ではなく18~25mm程度である。ちなみに、原始卵胞は0.03mm程度である。
2.〇 正しい。初経のころの原始卵胞数は、出生時より少ない。胎児の卵巣には600万~700万個の卵母細胞が存在し、卵母細胞の大半は次第に消失していき、出生時までに100万~200万個程度にまで減少する。思春期には約40万個となる。
3.× 排卵されなかった卵胞は、グラーフ卵胞と「ならずそのまま退化(閉鎖)する」。グラーフ卵胞とは、排卵直前まで十分に成熟した卵胞のことであり、まさにこれから排卵される卵胞を指す。排卵の機会を逃したり、十分に成熟できなかった卵胞は、通常、グラーフ卵胞にはならず、そのまま退化(閉鎖)する。
4.× 「プロゲステロン」ではなくインヒビンの作用によって排卵に至る卵胞が1つになる。
・インヒビンとは、脳下垂体前葉ホルモンである卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌を調節する蛋白質である。排卵に向けて1個のみの卵胞が選択される機序として卵胞刺激ホルモン(FSH)の血中濃度変化が関与するとされている。卵巣や精巣で作られ、黄体形成ホルモンに影響を与えることなく卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌を特異的に抑制する。したがって、副作用の少ない男性避妊薬としての応用が期待されている。
・プロゲステロン(黄体ホルモン)は、基礎体温を上げ、受精卵が着床しやすい状態にする作用を持つ。プロゲステロン(黄体ホルモン)は、性周期が規則的で健常な成人女性において、着床が起こる時期に血中濃度が最も高くなるホルモンである。着床が起こる時期とは、月経の黄体期である。黄体期は、排卵した後の卵胞(黄体)から黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されるようになる時期である。
5 男性不妊のリスク因子はどれか。
1.腎結石
2.低身長
3.両側鼠径ヘルニア修復術の既往
4.単純ヘルペスウイルスの感染の既往
解答3
解説
1.× 腎結石は、男性不妊の直接的なリスク因子ではない。
・腎結石とは、尿管から膀胱に向かって徐々に下降し、結石が膀胱に近づくと、膀胱を刺激し、頻尿や残尿感、腰背部に激しい痛みなどの症状が現れる。
2.× 低身長は、男性不妊の直接的なリスク因子ではない。生殖機能は、主にホルモンバランスや生殖器の形態・機能に依存する。
3.〇 正しい。両側鼠径ヘルニア修復術の既往は、男性不妊のリスク因子である。
・鼠径ヘルニア修復術とは、鼠径管内の精索(精管、精巣動脈、静脈などが含まれる)に近接して行われる。特に、両側で手術が行われた場合、手術操作によって精管が損傷を受けたり、精巣への血流が阻害されたりするリスクがあり、これが精子輸送の障害や精巣機能の低下につながる可能性がある。
4.× 単純ヘルペスウイルスの感染の既往は、男性不妊の直接的なリスク因子ではない。なぜなら、単純ヘルペスウイルスは、精巣機能や精子の形成、輸送に直接的に影響を及ぼさないため。
・単純ヘルペスウイルスとは、主に皮膚や粘膜に水疱を形成する感染症を引き起こす。
 希望の解説ブログ
希望の解説ブログ