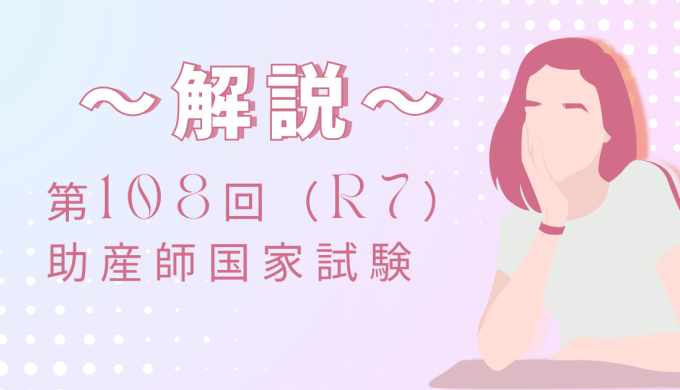この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
16 Aちゃん(4歳、男児)は幼稚園通園中である。有意語の発語が少なく指示が通じにくい、ごっこ遊びをしない、興味を持つおもちゃが限定されている、といった特徴から自閉スペクトラム症と診断されている。最近、不機嫌になって対応に困ることが多くなり、両親はAちゃんとの関わり方に悩んでいる様子である。
児への関わり方の指導で適切なのはどれか。
1.遊びの場になるべく多種類のおもちゃを置いておく。
2.興奮状態になった場合は1人になれる場所に誘導する。
3.Aちゃんに理解できないことは明確な言葉で繰り返し伝える。
4.Aちゃんの機嫌をみてその日のスケジュールをこまめに変更する。
解答2
解説
・Aちゃん(4歳、男児、自閉スペクトラム症)。
・幼稚園通園中:有意語の発語が少なく指示が通じにくい、ごっこ遊びをしない、興味を持つおもちゃが限定されている。
・最近:不機嫌になって対応に困ることが多い。
・両親:Aちゃんとの関わり方に悩んでいる。
→自閉症スペクトラム症とは、正常な社会的関係を構築することができず、言葉の使い方に異常がみられるか、まったく言葉を使おうとせず、強迫的な行動や儀式的な行動がみられる病気である。 自閉スペクトラム症の患者は、他者とコミュニケーションをとったり関係をもったりすることが苦手である特徴を持つ。
広汎性発達障害(自閉スペクトラム障害)とは、相互的な社会関係とコミュニケーションのパターンの障害、および限局・常同・反復的な行動パターンがあげられる。生後5年以内に明らかとなる一群の障害である。通常は精神遅滞を伴う。広汎性発達障害、およびその下位分類である自閉症、アスペルガー症候群、高機能自閉症は、「自閉スペクトラム症」とまとめられた。
【診断基準の要点】
①「社会及び感情の相互性の障害」「社会的相互作用で用いられる非言語的コミュニケーションの障害」「発達レベル相応の関係を築き維持することの障害」の3つがすべて込められること。
②行動、興味活動の、限局的で反復的な様式が認められること。
1.× あえて、遊びの場になるべく多種類のおもちゃを置いておく必要はない。なぜなら、Aちゃん(自閉スペクトラム症)は、興味を持つおもちゃが限定されており、多種類のおもちゃを置ことで、集中を妨げたり、どれを選んでいいか分からず困惑したりする原因になるため。
2.〇 正しい。興奮状態になった場合は、1人になれる場所に誘導する。なぜなら、自閉スペクトラム症の児は、感覚過敏やコミュニケーションの困難さから、ストレスや不安を感じやすく、それらが興奮やパニックとして現れることがあるため。したがって、感覚刺激の少ない静かな場所で、落ち着きを取り戻すための環境作りが必要となる。
3.× あえて、Aちゃんに理解できないことは明確な言葉で繰り返し伝える必要はない。なぜなら、Aちゃん(自閉スペクトラム症)は、指示が通じにくい特徴があり、言葉での理解に困難があるため。したがって、明確な言葉で繰り返しても、かえって混乱を招く可能性がある。言葉だけでなく、視覚的な情報(絵カード、写真、実物、ジェスチャーなど)を併用する必要がある。
4.× あえて、Aちゃんの機嫌をみてその日のスケジュールをこまめに変更する必要はない。なぜなら、一般的に自閉スペクトラム症の特徴として、強迫的な行動や儀式的な行動がみられるため。したがって、スケジュールのこまめな変更は、かえって混乱や不安を増幅させ、不機嫌を助長する可能性がある。あらかじめ決まったスケジュールやルーティンがあることで、安心感を得て落ち着いて過ごせる場合が多い。
17 低出生体重児について正しいのはどれか。
1.令和3年(2021年)の低出生体重児の割合は全出生の5%である。
2.低出生体重児の予後は在胎週数と相関しない。
3.3歳までに成長曲線を上回る。
4.成人後の肥満に関連がある。
解答4
解説
低出生体重児とは、2500g未満児のこと。1500g未満を「極低出生体重児」、1000g未満を「超低出生体重児」と呼ぶ。低体温、低血糖、貧血、黄疸(高ビリルビン血症)などが起こりやすく、感染への抵抗力も弱いため、外的ストレスをできる限り減らす。ポジショニングは、体内にいるときに近い姿勢を保つ。子宮内環境に近づける。
1.× 令和3年(2021年)の低出生体重児の割合は、全出生の「5%」ではなく約10%である(※引用:「人口動態調査 人口動態統計 確定数 出生」政府統計の総合窓口様HPより)。
2.× 低出生体重児の予後は、在胎週数と「相関する」。なぜなら、在胎週数が短い、すなわち未熟な状態で生まれるほど、呼吸器系、循環器系、神経系などの臓器が未発達であるため。したがって、重篤な合併症(呼吸窮迫症候群、脳室内出血、壊死性腸炎など)のリスクが高まり、予後が悪くなる傾向がある。
3.× 3歳までに成長曲線を「上回る」と断言できない。つまり、全ての児が3歳までに成長曲線を上回るわけではない。なぜなら、成長には少なからず個人差があり、栄養状態、合併症の有無、遺伝的要因などが影響するため。キャッチアップ現象がみられることが多いが、成長曲線の下限を下回って推移する児も少なくない。
・キャッチアップ現象とは、小児の発達段階で、成長や発達に重要な時期である臨界期以外の時期に、それまで病気や環境により成長が障害されていても、その状況が改善されると、体重や身長などの成長度合いが、障害前よりも速度を上げて追いつく現象のことである。
4.〇 正しい。成人後の肥満に関連がある。なぜなら、「Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD)」という概念が根拠となるため。胎児期や乳幼児期の栄養状態や成長環境が、成人後の生活習慣病(肥満、糖尿病、高血圧、心血管疾患など)のリスクに影響を与える。
子宮内での環境悪化をはじめとした発育期の環境変化による影響が,将来の成人期の疾病発症にかかわるとする Developmental Origin of Health and Disease(DOHaD)学説が注目を集めている。この学説は,1920年代の新生児死亡率と約半世紀後の虚血性心疾患による死亡の相関の報告に始まり,「胎児期の環境悪化に適応するために低出生体重となることにより内分泌代謝の恒常性が変化し,そのことが成人期の生活習慣病リスクを上昇させる」という仮説が提唱された。Gluckmanらはこの仮説をより一般化し,「発達期の個体において環境の変化に対応した不可逆的な変化が生じ,このような変化が発達の完了した時期の環境に適応できなければそれは成人期に種々の疾患の源となる」というDOHaD仮説として定着するようになった。この仮説は多くの疫学研究や動物実験によっても支持されている。これまでの大規模疫学研究により,低出生体重が冠動脈疾患,高血圧,脳卒中,糖尿病,肥満,メタボリックシンドロームなどの多様な非感染性疾患(non-communicative disease:NCD)の発症リスクを増加させることが明らかになっている。極端な例として人類の歴史上不幸にして起こった飢餓事件の追跡コホート研究があり,胎児期に飢餓に直面することにより成人後に生活習慣病の増加が引き起こされる例が報告されている。
(一部引用:「Developmental Origin of Health and Disease(DOHaD)学説と腎臓」著:張 田 豊より)
18 高校2年生を対象に、将来の妊娠も視野に入れた健康づくりをテーマに助産師が健康教育を行うことになった。
説明で適切なのはどれか。
1.「バランスのよい食事で適正な体重を維持しましょう」
2.「スポーツは1日60分、1週間300分を目安に行いましょう」
3.「結婚したら、女性は速やかにかかりつけの婦人科医院をつくりましょう」
4.「幼児期に風しんワクチンを受けていても妊娠初期に再度接種しましょう」
解答1
解説
・対象:高校2年生
・テーマ:将来の妊娠も視野に入れた健康づくり
・助産師が健康教育を行う。
1.〇 正しい。「バランスのよい食事で適正な体重を維持しましょう」と説明する。なぜなら、高校2年生の時期からバランスの取れた食生活を送り、適切な体重を維持することは、将来の妊娠・出産だけでなく、生涯にわたる健康の基盤となるため。肥満や痩せすぎは、妊娠中の合併症(妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群、低出生体重児など)のリスクを高める。
2.× 「スポーツは1日60分、1週間300分を目安に行いましょう」と伝える必要はない。なぜなら、「スポーツ」という限定的な表現に誤解を生む可能性があるため。必ずしもスポーツである必要はなく、有酸素運動(例えば、歩行や散歩、家事、階段の利用)を行う。つまり、日常生活における身体活動も重要であることを伝える。
3.× 「結婚したら、女性は速やかにかかりつけの婦人科医院をつくりましょう」と伝える必要はない。なぜなら、「結婚」という条件で限定する必要はないため。一般的に、思春期以降からかかりつけの婦人科医院を持つことが望ましい。これは、結婚前で妊娠したり、性成熟期の女性は、月経不順、性感染症予防、がん検診、避妊相談なども考えられるためである。
4.× 「幼児期に風しんワクチンを受けていても妊娠初期に再度接種しましょう」と伝える必要はない。なぜなら、風しんワクチンは生ワクチンであるため。したがって、妊娠中は接種できない。妊娠中に風しんに感染すると、先天性風しん症候群として胎児に重篤な影響を及ぼす可能性がある。妊娠を希望する女性は、妊娠前に免疫の有無を確認し、免疫がない場合は妊娠前にワクチンを接種しておく必要がある。
・風疹とは、発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とするウイルス性発疹症である。症状として、難聴・白内障・心奇形である。妊婦が妊娠初期に風疹に感染すると、不顕性であっても経胎盤的に胎児に影響を与え、先天性風疹症候群と呼ばれる先天異常を引き起こすことがある。
先天性風疹症候群とは、風しんウイルスの胎内感染(垂直感染)によって先天異常を起こす感染症である。 3徴は、白内障、先天性心疾患、難聴である。その他先天性緑内障、色素性網膜症、紫斑、脾腫、小頭症、精神発達遅滞、髄膜脳炎、骨のX線透過性所見、生後24時間以内に出現する黄疸などを来しうる。臨床的特徴として、先天異常の発生は妊娠週齢と明らかに相関し、妊娠12週までの妊娠初期の初感染に最も多くみられ、20週を過ぎるとほとんどなくなる。
19 A病院は母体・胎児集中治療室〈MFICU〉を持たない総合病院である。
A病院の産科病棟の管理で正しいのはどれか。
1.空床に他科の患者を受け入れることができる。
2.助産師の配置人数は診療報酬で規定されている。
3.母児同室をする病室の床面積は診療報酬で規定されている。
4.正常新生児6名に1名の看護職員を配置しなければならない。
解答1
解説
母体・胎児集中治療室とは、妊婦に重症妊娠高血圧症候群・重篤な合併症・多胎妊娠などのリスクがある場合や、胎児に切迫早産・疾患が予想される場合に、妊婦や胎児が入院する施設である。患者さんの状況に応じてNICU・GCU・小児科のほか、さまざまな診療科と連携を図りながら24時間体制で対応する。
1.〇 正しい。空床に他科の患者を受け入れることができる。MFICU(母体・胎児集中治療室)を持たない総合病院の場合、病院全体のベッド稼働率や効率的な医療資源の利用の観点から、必要に応じて他科の患者を受け入れることが許容されている。ただし、感染管理や患者の特性(例えば、未熟児のいる環境に感染症の患者を入れるのは避けるなど)には十分な配慮が必要である。
2.× 助産師の配置人数は、「診療報酬で規定」されていない。ちなみに、病棟の種類(産科病棟、MFICUなど)や提供する医療の内容によって推奨される基準がある。安全・安心な出産環境を確保するため、産科病棟では常勤の助産師が3名以上配置されていること、そのうち1名以上が医療関係団体から認証された助産師であることが、一部の保険医療機関における施設基準として挙げられる。
・診療報酬とは、医師や看護師などから受ける医療行為に対して、保険制度が支払う料金である。
3.× 母児同室をする病室の床面積は、「診療報酬で規定」されていない。ちなみに、一般的な病室の基準であり、母児同室かどうかにかかわらず適用される。病院の病室の床面積に関する基準は、医療法で定められている。例えば、病室の床面積は「1患者につき6.4平方メートル以上」と規定されている。
・医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。
4.× 正常新生児6名に1名の看護職員を配置しなければならないと規定されているのは、「周産期母子医療センター」の基準である。ほかにも、①新生児集中治療管理室(NICU)は、3:1であり、②集中治療管理室(ICU)は、2:1という基準がある。
周産期母子医療センターには、①総合周産期母子医療センターと②地域周産期母子医療センターがある。
①総合周産期母子医療センターとは、母体・胎児集中治療管理室(M-FICU)を含む産科病棟及び新生児集中治療管理室(NICU)を備えた医療機関である。常時、母体・新生児搬送受入体制を有し、母体の救命救急への対応、ハイリスク妊娠に対する医療、高度な新生児医療等を担っている。
②地域周産期母子医療センターとは、産科及び小児科(新生児)を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を常時担う医療機関である。
20 出産扶助について適切なのはどれか。
1.自宅分娩は支給対象外である。
2.分娩介助費は実費で支給される。
3.分娩前の処置は支給対象ではない。
4.分娩後の衛生材料は現物支給される。
解答2
解説
出産扶助とは、生活保護の扶助の1つで、出産のために必要な費用の支給を受けることができる。出産にあたって、保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由で病院又は助産所に入院できない妊産婦で、出産前に申請した場合に対象となる。
1.× 自宅分娩は「支給対象外」ではなく支給対象内である。なぜなら、出産扶助は、出産にかかる費用を保障するものであるため。したがって、分娩場所は問われず、病院、診療所、助産所、さらには自宅での分娩であっても、必要と認められる費用であれば支給の対象となる。
2.〇 正しい。分娩介助費は、実費で支給される。なぜなら、出産扶助は、出産に必要な費用を、厚生労働大臣が定める基準に基づいて支給することになっているため。
・分娩介助料とは、分娩介助費ともいい、分娩時に異常が発生した際の助産師のサポートに対して請求される費用である。鉗子娩出術、吸引娩出術などで行われる会陰保護の費用も含まれる。したがって、分娩介助料は自費分についての費用であり、保険給付分は含まれない。
3.× 分娩前の処置「も」支給対象「である」。なぜなら、出産を円滑に進める上で不可欠なため。例えば、分娩に直接関連する診察、検査、処置などが含まれる。
4.× 分娩後の衛生材料は、「現物支給」ではなく現金支給される。
・生活保護法とは、『日本国憲法』25条の理念に基づき、生活困窮者を対象に、国の責任において、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。8つの扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、原則現金給付であるが、医療扶助と介護扶助は現物給付である。
生活保護制度は、『日本国憲法』25条の理念に基づき、生活困窮者を対象に、国の責任において、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。8つの扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、原則現金給付であるが、医療扶助と介護扶助は現物給付である。被保護人員は約216.4万人(平成27年度,1か月平均)で過去最高となっている。
生活扶助:日常生活に必要な費用
住宅扶助:アパート等の家賃
教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
医療扶助:医療サービスの費用
介護扶助:介護サービスの費用
出産扶助:出産費用
生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
葬祭扶助:葬祭費用
【生活保護法の4つの基本原理】
①国家責任の原理:法の目的を定めた最も根本的原理で、憲法第25条の生存権を実現する為、国がその責任を持って生活に困窮する国民の保護を行う。
②無差別平等の原理:全ての国民は、この法に定める要件を満たす限り、生活困窮に陥った理由や社会的身分等に関わらず無差別平等に保護を受給できる。また、現時点の経済的状態に着目して保護が実施される。
③最低生活の原理:法で保障する最低生活水準について、健康で文化的な最低限度の生活を維持できるものを保障する。
④保護の補足性の原理:保護を受ける側、つまり国民に要請される原理で、各自が持てる能力や資産、他法や他施策といったあらゆるものを活用し、最善の努力をしても最低生活が維持できない場合に初めて生活保護制度を活用できる。
【4つの原則】
①申請保護の原則:保護を受けるためには必ず申請手続きを要し、本人や扶養義務者、親族等による申請に基づいて保護が開始。
②基準及び程度の原則:保護は最低限度の生活基準を超えない枠で行われ、厚生労働大臣の定める保護基準により測定した要保護者の需要を基とし、その不足分を補う程度の保護が行われる。
③必要即応の原則:要保護者の年齢や性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行われる。
④世帯単位の原則:世帯を単位として保護の要否及び程度が定められる。また、特別な事情がある場合は世帯分離を行い個人を世帯の単位として定めることもできる。
(※参考:「生活保護制度」厚生労働省HPより)
(※参考:「生活保護法の基本原理と基本原則」室蘭市HPより)
 希望の解説ブログ
希望の解説ブログ