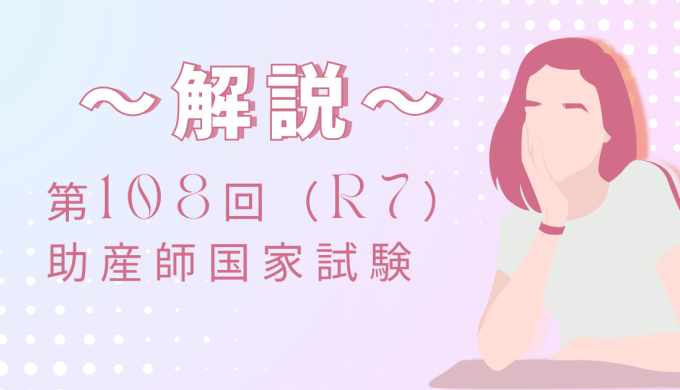この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
31 母性健康管理指導事項連絡カードについて正しいのはどれか。2つ選べ。
1.母体保護法に規定されている。
2.措置が必要となる症状に産後の不安がある。
3.措置が必要な期間を延長する場合は新たに発行する。
4.必要な措置を講じることは事業主の努力義務である。
5.女性従業者は診断書を添えて事業主に必要な措置を申請する。
解答2・3
解説
母性健康管理指導事項連絡カードとは、妊娠中および出産後の女性従業員が、病院やクリニックから指導を受けた内容を適切に事業主に伝達するための書類で、通称「母健連絡カード」と呼ばれる。母性健康管理指導事項連絡カードの記載は、助産師(もくしは医師も)が行える。
1.× 「母体保護法」ではなく男女雇用機会均等法(第13条)に規定されている。これは、妊娠中や出産後の女性労働者が医師等から指導を受けた際に、その内容を事業主に的確に伝えるためのツールであり、法的な義務付けがある。
・男女雇用機会均等法の第十三条には「事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない」と記載されている(※「男女雇用機会均等法」e-GOV法令検索様HPより)。
・母体保護法とは、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する堕胎罪の例外事項を定めること等により、母親の生命健康を保護することを目的とした法律である。1948年7月13日に公布された。
2.〇 正しい。措置が必要となる症状に「産後の不安」がある。措置が必要となる症状において、「つわり、妊娠悪阻、貧血、めまい・立ちくらみ、腹部緊満感、子宮収縮、腹痛、性器出血、腰痛、痔、静脈瘤、浮腫、手や手首の痛み、頻尿、排尿時痛、残尿感、全身倦怠感、動悸、頭痛、血圧の上昇、蛋白尿、妊娠糖尿病、赤ちゃん(胎児)が週数に比べ小さい、多胎妊娠( 胎)、産後体調が悪い、妊娠中・産後の不安・不眠・落ち着かないなど」があげられる(※引用:「母健連絡カード」厚生労働省様HPより)。
3.〇 正しい。措置が必要な期間を延長する場合は新たに発行する。母性健康管理指導事項連絡カードは、医師や助産師が指導を行った時点での必要な措置と期間を記載するものである。もし当初の期間が終了した後も、引き続き同じ、あるいは別の措置が必要となった場合は、その都度、医師等による再診察を受け、新たな指導に基づいた連絡カードを改めて発行してもらう必要がある。これにより、事業主は最新の医学的知見に基づいた適切な措置を講じることができる。
4.× 必要な措置を講じることは事業主の「努力義務」ではなく義務である。男女雇用機会均等法第13条において、「その指導内容に応じた適切な措置を講じなければならない」と義務付けられいるため。ちなみに、努力義務は、努めなければならないといったものである。
5.× 必ずしも、女性従業者は「診断書」を添えて事業主に必要な措置を申請する必要はない。なぜなら、厚生労働省が定めているのは「母性健康管理指導事項連絡カード」であり、このカード自体が医師や助産師の指導内容を事業主に伝える公的な書類としての役割を果たすため。したがって、女性従業員は、医師等からこのカードの発行を受け、それを事業主に提出することで、必要な措置を申請できる。これは、診断書よりも、詳細な病状説明が可能となる処置である。
32 Aさん(40歳、初産婦)は、骨盤位のため38週0日に帝王切開で分娩する方針になった。非妊時のBMI30、喫煙者であることから、静脈血栓塞栓症の発症を予防するため、術後に抗凝固療法が予定されている。
Aさんに手術後に行う対応で適切なのはどれか。2つ選べ。
1.直接授乳の中止
2.臥床時の頭部挙上
3.3日間のベッド上安静
4.間欠的空気圧迫法の実施
5.初回歩行時の助産師の付き添い
解答4・5
解説
・Aさん(40歳、初産婦、骨盤位)
・方針:38週0日に帝王切開で分娩する。
・非妊時のBMI30、喫煙者である。
・静脈血栓塞栓症の発症を予防する。
・術後に抗凝固療法が予定されている。
→静脈血栓塞栓症とは、手足の静脈に血栓ができて血管が詰まる深部静脈血栓症(DVT)と、その血栓が血流に乗って運ばれ肺の動脈に詰まる肺血栓塞栓症を合わせた総称である。深部静脈血栓症とは、長時間の安静や手術などの血流低下により下肢の静脈に血栓が詰まってしまう病気である。下肢の疼痛、圧痛、熱感などの症状がみられる。ほかのリスク因子として、脱水や肥満、化学療法などがあげられる。
1.× 直接授乳の中止は必要ない。なぜなら、帝王切開後の授乳は、特に問題がなければ早期から安全に開始することができるため。手術による痛みや体力の消耗があっても、適切な鎮痛とサポートがあれば直接授乳は可能である。また、術後には抗凝固療法が予定されているが、一般的に使用されるヘパリン製剤などは母乳移行が少なく、授乳は継続できる。
2.× 臥床時の頭部挙上は必要ない。なぜなら、頭部挙上と静脈血栓塞栓症の発症を予防との関連性は低いため。一般的に臥床時の頭部挙上は、呼吸困難のある患者や誤嚥のリスクがある患者に対して行われる。静脈血栓塞栓症の予防には、早期離床や下肢の運動による血栓予防の方が重要である。
3.× 3日間のベッド上安静は必要ない。なぜなら、ベッド上安静は、血液循環の停滞を招き、むしろ静脈血栓塞栓症のリスクを高めるため。静脈血栓塞栓症の予防には、早期離床や下肢の運動による血栓予防の方が重要である。
4.〇 正しい。間欠的空気圧迫法の実施をAさんに手術後に行う。なぜなら、間欠的空気圧迫法や軽擦法マッサージにより、循環改善が見込め、静脈血栓塞栓症の予防が期待できるため。
5.〇 正しい。初回歩行時の助産師の付き添いをAさんに手術後に行う。なぜなら、帝王切開術後は、麻酔の影響、手術による痛み、出血、長期臥床などにより、めまいやふらつき、貧血などの症状が出やすく、転倒のリスクが高いため。体調不良の際にもすぐ対応できる。
33 Aさん(25歳、初産婦)は、10年前にてんかんと診断され、抗てんかん薬の内服で現在の病状は安定している。妊娠38週0日で3,800gの男児を経腟分娩で出産した。羊水混濁なし、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点であった。児は生後2時間、啼泣時に軽度の下顎、四肢のふるえがみられる。努力呼吸や心雑音はない。体温37.0℃、呼吸数50/分、心拍数140/分、血圧60/40mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)である。
この児で今後、気を付けなければならないのはどれか。2つ選べ。
1.離脱症候群
2.新生児低血糖
3.先天性心疾患
4.胎便吸引症候群
5.新生児一過性多呼吸
解答1・2
解説
・Aさん(25歳、初産婦、10年前:てんかん)
・抗てんかん薬の内服で現在の病状は安定。
・妊娠38週0日:3,800gの男児を経腟分娩で出産。
・羊水混濁なし、アプガースコアは1分後8点、5分後9点。
・児は生後2時間、啼泣時に軽度の下顎、四肢のふるえがみられる。
・努力呼吸や心雑音はない。
・体温37.0℃、呼吸数50/分、心拍数140/分、血圧60/40mmHg、SpO2:98%。
→上記評価の正常範囲内をしっかり把握し、選択肢の症状をおさえておこう。
1.〇 正しい。離脱症候群を今後、気を付けなければならない。なぜなら、母親が妊娠中に抗てんかん薬を内服していた場合、薬剤の種類によっては胎盤を通過し、胎児の体内に蓄積することがあるため。出生後、胎児が母体からの薬物の供給を断たれると、体内の薬物濃度が急激に低下し、薬物離脱症候群を発症する可能性がある。設問の新生児の軽度のふるえは、この離脱症候群の初期症状である可能性がある。
・新生児薬物離脱症候群とは、お産の前に投与された薬や常用している嗜好品が、胎盤を通過して生まれてきた赤ちゃんに一時的な効果を及ぼし、その物質が赤ちゃんの体から排泄される過程で、赤ちゃんの脳、消化管や自律神経の症状が一時的に現われることです。脳の症状として、筋肉の緊張がなくなってグッタリしたり、不安興奮状態で手足をブルブルふるったりすることがあります。もっと重い症状として、息を止めたり、けいれんしたりすることがあります。消化管の症状として、下痢や嘔吐がみられる場合もあります。自律神経の症状として、たくさん汗をかいたり、熱をだしたりします。この原因として、てんかんの治療薬、不安感などの精神の安定をはかる薬、鎮 痛薬や喘息の治療に使う飲み薬などです。嗜好品には、アルコー ルやカフェイン、非合法の麻薬などがあります「※一部引用:「重篤副作用疾患別対応マニュアル 新生児薬物離脱症候群」厚生労働省HPより」。
2.〇 正しい。新生児低血糖を今後、気を付けなければならない。なぜなら、母親が抗てんかん薬を内服している場合、薬剤の種類によっては、胎児の膵臓からのインスリン分泌に影響を与えたり、肝臓での糖新生を抑制したりすることで、新生児の低血糖リスクを高めることがあるため。また、設問の出生体重が3,800gと大きいこと(巨大児は出生体重が4000g以上)も、母体の妊娠糖尿病がなくても、胎児がインスリン過剰分泌を起こしているリスクを示唆し、低血糖になりやすい要因となる。設問の新生児の軽度のふるえは、低血糖の初期症状である可能性もある。
3.× 先天性心疾患より優先されるものが他にある。なぜなら、本児のアプガースコアが良好であり、生後2時間時点で心雑音がないため。
4.× 胎便吸引症候群より優先されるものが他にある。なぜなら、本児のアプガースコアが良好であり、生後2時間時点で努力呼吸がないため。
・胎便吸引症候群とは、出生前または周産期に肺に胎便(暗緑色の、無菌の便)を吸い込んだ新生児にチアノーゼや呼吸困難(呼吸窮迫)がみられることである。酸素不足などのストレスによって反射的にあえぎ、胎便を含む羊水を肺に吸い込んでしまうことなどで起こる。多呼吸、羊水混濁が特徴である。胸部エックス線の所見の特徴では、①両肺野にびまん性の策状影、②縦郭気腫などのエアリーク所見、③両側肺の過膨張がみられる。
5.× 新生児一過性多呼吸より優先されるものが他にある。なぜなら、本児のアプガースコアが良好であり、生後2時間時点で努力呼吸がないため。
・新生児一過性多呼吸とは、出生後に胎児肺液の吸収が遅れることにより、一過性に多呼吸や努力呼吸を呈する疾患で、酸素化は比較的保たれ、数日以内に自然軽快する。ちなみに、多呼吸とは、浅くて速い呼吸のことである。基準値として、新生児は60回/分以上、乳児は50回/分以上、幼児は40回/分以上である。主に肺炎など肺のコンプライアンスが減少するために1回換気量が不足し、呼吸回数で補おうとする。多呼吸の原因として、他にも肺の未熟性、感染症、心不全、代謝異常などがあげられる。
34 乳児家庭全戸訪問事業〈こんにちは赤ちゃん事業〉について正しいのはどれか。2つ選べ。
1.実施主体は都道府県である。
2.訪問の担当者には子育て経験者が含まれる。
3.育児相談や子育て支援に関する情報提供を行う。
4.対象は生後6か月までの乳児がいる全家庭である。
5.児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に基づき実施される。
解答2・3
解説
乳児家庭全戸訪問事業は、児童福祉法(第6条の3)に規定されている。児童福祉法(第6条の3)「この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう」と記載されている(※引用:「児童福祉法」e-GOV法令検索様HPより)。
1.× 実施主体は、「都道府県」ではなく市町村である。なぜなら、市町村が実施主体にすることで、きめ細やかな支援を提供することができるため。
2.〇 正しい。訪問の担当者には「子育て経験者」が含まれる。なぜなら、専門職(愛育班員、母子保健推進員、児童委員など)だけでは手が回らない場合や、より生活に密着した支援、あるいは親に寄り添った共感的な関わりが求められる場合に、子育て経験者の知見や共感力が有効であるとされているため。訪問スタッフには、愛育班員、母子保健推進員、児童委員、子育て経験者等を幅広く登用する。
3.〇 正しい。育児相談や子育て支援に関する情報提供を行う。乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)の事業の目的は、「生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなげる。このようにして、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図るものである」(※引用:「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」厚生労働省様HPより)。
4.× 対象は、「生後6か月」ではなく生後4か月までの乳児がいる全家庭である(選択肢3を参照)。
5.× 「児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉」ではなく児童福祉法に基づき実施される(※解説上参照)。
・児童福祉法とは、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律である。児童が良好な環境において生まれ、且つ、心身ともに健やかに育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対策を含むすべての児童の福祉を支援する法律である。
・児童虐待の防止等に関する法律とは、児童虐待防止に関する施策を促進し、児童の権利・利益を擁護することを目的としている。児童に対する虐待の禁止、虐待に関する地方自治体の責務、児童の保護措置などが規定されている。
35 保健師助産師看護師法に記載されている助産師の義務はどれか。2つ選べ。
1.就業の届出
2.出生証明書の交付
3.受胎調節実地指導
4.新生児の訪問指導
5.助産所開設時の届出
解答1・2
解説
1.〇 正しい。就業の届出は、保健師助産師看護師法に記載されている助産師の義務である。
・保健師助産師看護師法第33条では、「業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない」と規定されている(※引用:「保健師助産師看護師法」e-GOV法令検索様HPより)。
2.〇 正しい。出生証明書の交付は、保健師助産師看護師法に記載されている助産師の義務である。
・保健師助産師看護師法の第39条2項において「分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められている(※引用:「保健師助産師看護師法」e-GOV法令検索様HPより)。
3.× 受胎調節実地指導は母体保護法に規定されている。これは、母体保護法の(受胎調節の実地指導)15条2項に「前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする」と規定されている(※一部引用:「母体保護法」e-GOV法令検索様HPより)。
・受胎調節実地指導員とは、女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導を行う者として都道府県知事の指定を受けた人のことである。避妊をすることによって妊娠、出産を計画的に調節することを受胎調節という。
4.× 新生児の訪問指導は母子保健法に規定されている。平成9年の母子保健法の改正内容は、主に母子保健事業の実施基盤の整備である。①妊産婦又は乳幼児の保護者に対する保健指導、新生児の訪問指導、3歳児健康診査及び妊産婦の訪問指導の実施主体を市町村とすること。②市町村の行う健康診査の対象に満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児を加えること。③妊娠、出産又は育児に関する保健指導の対象に妊産婦の配偶者を加えること。④国及び地方公共団体は、妊産婦及び乳幼児に対し高度な医療が提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならないこととしたこと。⑤国は、母性及び乳幼児の健康の保持増進に必要な調査研究の推進に努めなければならないこととしたこと。⑥母子保健事業の体制整備のための所要の規定の整備すること(※引用:「母子保健法の改定とこれからの母子保健」著:富沢一郎)。
5.× 助産所開設時の届出は医療法に定められている。医療法の第8条において「臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない」と定められている(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。
・医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。
 希望の解説ブログ
希望の解説ブログ